「副業としてブログを始めれば、自分にも稼げるかもしれない」
そう思って、私はブログに挑戦しました。
文章を書くこと自体は嫌いじゃないし、在宅でできるのも魅力的。
「継続さえできれば、そのうち結果が出るはず」と、軽い気持ちでスタートしたのを覚えています。
でも、現実はそんなに甘くありませんでした。
記事を書き続けることが、想像以上に難しかった。
気づけば、ブログの更新は止まり、私は静かに挫折していました。
なぜ続けられなかったのか?
今振り返ってみると、その理由は「ネタ切れ」だけじゃなかったと気づきました。
テーマ選び、記事の構成、そしてブログ全体の運用設計――
書き始める前に考えるべきことを、私は何も知らなかったのです。
この記事では、ブログ副業に挫折した私の実体験をもとに、
「なぜ続けられなかったのか」
「それでもやってよかったと思える理由」
を正直に綴っていきます。
ブログを始めようか悩んでいる方や、同じように手が止まってしまった方の、ヒントになれたらうれしいです。
私のブログ運営失敗談の全ては以下記事を読んでください!
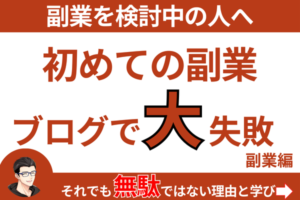
すぐにネタ切れになった理由
ブログを始めた当初、私は「資格の合格体験」をテーマにしていました。
自分が勉強してきた経験をまとめれば、同じように資格取得を目指す人の役に立つはず。そう思ったのです。
最初はスムーズに記事を書けました。
受験前の勉強法、試験当日の流れ、使った教材の紹介など、書くネタはいくつか思いついたし、実際に誰かの役に立っている実感もありました。
でも、そのペースは長くは続きませんでした。
資格というテーマは、新しい合格体験を積み重ねない限り、記事を増やしにくいジャンルです。
私は「資格を取った経験」を切り口にしていたため、次の資格に合格しないと、新しい記事のネタが生まれません。
にもかかわらず、次の資格試験を受ける予定も立てられず、時間も気力も残っていない。
書きたいことは尽きていき、「何を書けばいいかわからない」状態に陥りました。
無理にネタを絞り出しても、薄い内容になってしまう。
検索される見込みもなく、「こんな記事誰が読むんだろう」と思うようになり、どんどん手が止まっていきました。
記事の書き方にも落とし穴があった
記事ネタが思いつかなくなってきた頃、
「とにかく書けば何とかなるはず」と思いながら、私は構成を考えずにいきなり本文から書き始めていました。
でもこの方法は、すぐに限界が来ました。
何を書いているのか途中でわからなくなり、
話があちこちに飛んで、自分でもよくわからない記事になってしまう。
書くのに時間はかかるのに、読みやすくもないし、
「これじゃダメだよな…」とわかっているのに、どう直せばいいかもわからない。
そんな苦しさの中で、ますます手が止まっていきました。
今ならわかるのですが、記事の構成を考えずに書くのは、地図なしで知らない街を歩き回るようなものです。
「誰に、何を、どう伝えるか」が決まっていなければ、読者にも響かないし、自分の疲労感も大きくなります。
当時の私は、「構成=難しそう」と思い込んで避けていました。
でも実際には、構成こそが“書きやすさ”と“読まれやすさ”を両立させる鍵だったのです。
ブログ全体の運用設計ができていなかった
今振り返ると、私がブログを続けられなかった一番の理由は、記事単体だけでなく、ブログ全体の“設計図”がなかったことだと思います。
当時の私は、思いついたネタをただ順番に書いて投稿していただけでした。
「このブログは誰のために、何を提供するのか?」
「どんなカテゴリで構成して、どういう流れで読んでもらうのか?」
そんな全体の構想を、まったく持っていなかったんです。
結果、ブログの中に統一感がなく、読み手にとっても「どんなブログなのか」がわかりづらかったと思います。
記事の内容もバラついていて、自分自身でも「これ、何のブログなんだろう…?」と感じるようになっていきました。
また、運営のゴールや目標も曖昧なまま始めていたため、
「何記事書けばいいのか」「どうすれば成果につながるのか」が分からず、やりがいも見失ってしまいました。
ブログは、ただ書けばいいというものではなく、
「誰に、どんな価値を届けるか」を設計しておくことで、継続しやすくなる。
今ならそう思えますが、当時はまったくその視点がなかったことが、大きな落とし穴でした。
リサーチ不足も続かない原因だった
ブログを始めた頃の私は、「とにかく自分の経験を書けば誰かの役に立つはず」と信じていました。
その気持ち自体は間違っていなかったと思います。
でも、今思えばあまりにもリサーチが足りなかった。
検索されるキーワードを調べることもせず、
他の人がどんな記事を書いているのか、どんな悩みに答えているのか――
そういった情報をまったく見ないまま、自分の中にあることだけで記事を書いていたんです。
その結果、誰にも検索されない、誰にも届かない記事が積み上がっていきました。
「せっかく時間をかけて書いたのに、誰も読んでいない」
そんな虚しさが積もり、どんどんモチベーションが削られていきました。
リサーチとは、ただネタを探すためだけのものではなく、
「自分の書く記事を、必要とする人に届けるための準備」でもあると、今ならわかります。
それでもやってよかったと思える理由
続けられなかった。成果も出なかった。
それでも私は、「ブログをやってみてよかった」と今では思っています。
理由のひとつは、書くという行為を通して、自分の考えを整理する習慣ができたこと。
たとえ誰かに読まれなくても、「自分が何を伝えたいのか」を考えながら言語化することは、それだけで価値のある経験でした。
また、ブログで得た経験は、その後挑戦した副業にも活きています。
たとえば、オンライン秘書としてクライアントの業務をサポートするときには、
「わかりやすく、簡潔に伝える」「情報を整理してまとめる」といった力が役立ちました。
さらに、Webライティングに挑戦した際には、
「構成を考える」「読者を意識する」「文章の流れに気を配る」といったスキルが、ブログを通じてある程度身についていたことに気づきました。
そして何より、「続かなかった」という事実からも、大切なことに気づけました。
自分には、明確な設計や目標がないと続けづらいタイプなんだということ。
これは今の働き方や副業選びにおいて、判断基準のひとつになっています。
結論:ネタ切れは“才能のせい”じゃない
ブログを始めた当時の私は、「ネタが続かない=自分には向いていないんだ」と思い込んでいました。
でも今なら、そうじゃなかったと断言できます。
続かなかった理由は、準備や設計が足りなかったから。
テーマの選び方、記事の構成、読者やキーワードのリサーチ、そしてブログ全体の運用設計――
どれも知らずに始めていたら、途中で行き詰まるのは当然だったのです。
もしも今、ブログを始めてみたいと思っている方がいたら、こう伝えたいです。
ネタ切れになっても、それは「センスがない」わけじゃない。
書けなくなっても、それは「努力が足りない」わけじゃない。
「どうやったら続けられるか」「どんな準備が必要か」を学べば、
書くことはもっと楽に、そして楽しくなっていきます。
そしてたとえ続けられなかったとしても、その経験は絶対にムダにはなりません。
私はそう信じています。
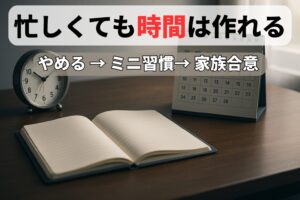

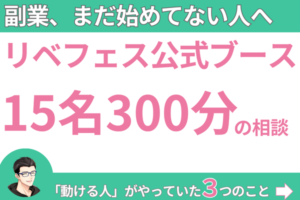

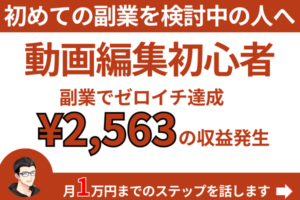
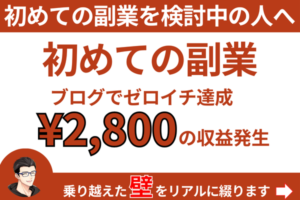
コメント